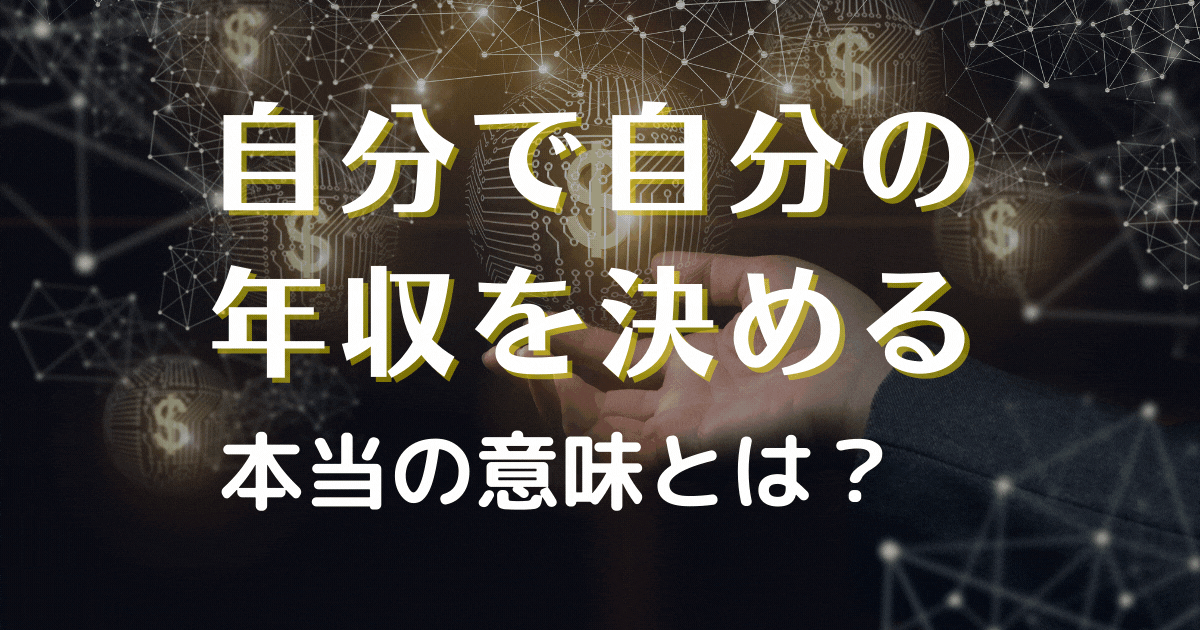
私はまだ20代の時、ある本で「独立起業したら、自分の年収は自分で決める」と書かれていることを読んだことがありました。
サラリーマン時代や実際に独立起業した直後はよくわからなかったのですが、独立起業後数年経過して、その本質的な意味が理解できました。
これは、「雇われる側と雇う側の決定的な違い」にも関係してくることなのですが、もしあなたがまだ雇われたことしかない場合や、独立起業間もない場合、またもしかしたら独立起業後何年も経っている場合であっても、このことに気づいていないかもしれないので、一読頂ければと思います。
①サラリーマンの場合
この場合、会社があなたの給料を決めることになるのでそのままなのですが、この場合であっても、転職の際には「給与交渉」ができる余地があるということを忘れてはなりません。
サラリーマンというのは会社があなたの給料を保障してくれるように錯覚しているかもしれませんが、実はそうではなくて「雇用契約」という契約にもとづいた労働形態なのです。
つまり、本質的には「派遣契約」や「業務委託契約」と同じように1つの契約形態にすぎないのです。
そう考えると、先に述べた給与交渉が可能だということも十分わかってもらえるのではないでしょうか?
②自営業(個人事業主)の場合
サラリーマンとは違い、やったらやった分だけ稼ぐことができます。ただ、「やったらやった分だけ」という点がポイントで、やらなければ稼げないし、頑張っても稼げないことも当然あります。
また、年収を意識するのは確定申告の時期で、実際に1年の売上と必要経費を計算してみて、はじめてその年の年収が確定することになります。
③自営業(会社役員)の場合
自分の法人を立ち上げ、代表取締役などの役員となった場合、実は会社の会計期間のはじめに年収は確定しています。
税法において、「会計期間が始まって2ヶ月以内に役員報酬を設定しなければならない」というルールがあるからです。
不思議に感じるかもしれませんが、これからの1年間で幾ら稼げるかもわからない段階で、予測で良いので決めなければならないのです。
ではここで、仮に役員報酬を月100万円に設定したとしよう。
年間合計だと1,200万円になります。
もちろん、自分の会社から払うので、実質的にはあなたが払うことになります。
税務上は会社から役員に支払ったことにして、その分の税金と社会保険料は払わなければなりません。
実質的に払っていないにも関わらず税金だけ発生するのは実に理不尽な気がすると思いますが、だからこそ、必死で稼ごうとするわけですね。
つまり、会社経営をしている人間からすれば、まだ稼ぎはじめる前に自分の目標収入を決め、それにもとづいて行動をしなければならない、ということです。
実運用上は節税対策などがあるので、見た目の年収を下げることも可能ですが、会社経営者は皆、実質的に自分が幾ら稼いでいるのかというのは、肌感覚で理解しています。
なので、もし自分が年収1億円が欲しいと思えば、まずは自分の中でその目標設定を行い、それに基づいた行動計画を練ることになります。
当然ながら、実質年収1,000万を目指すのと、実質年収1億円を目指すのとでは、難易度も変わるしやるべきことも変わるし、ビジネスモデルも変わってきます。
つまり、「自分で自分の年収を決める」という言葉の本質的な意味は、「自分で目標を立て、それに対してコミット(約束)する」ということなのです。
そういう意味では、まずは単純に自分が幾ら欲しいか考えれば良いわけです。
すると、それを実現する方法は自然と後からわかってきます。
 このサイトのコンテンツは現在進行系でアップデートしています。
このサイトのコンテンツは現在進行系でアップデートしています。