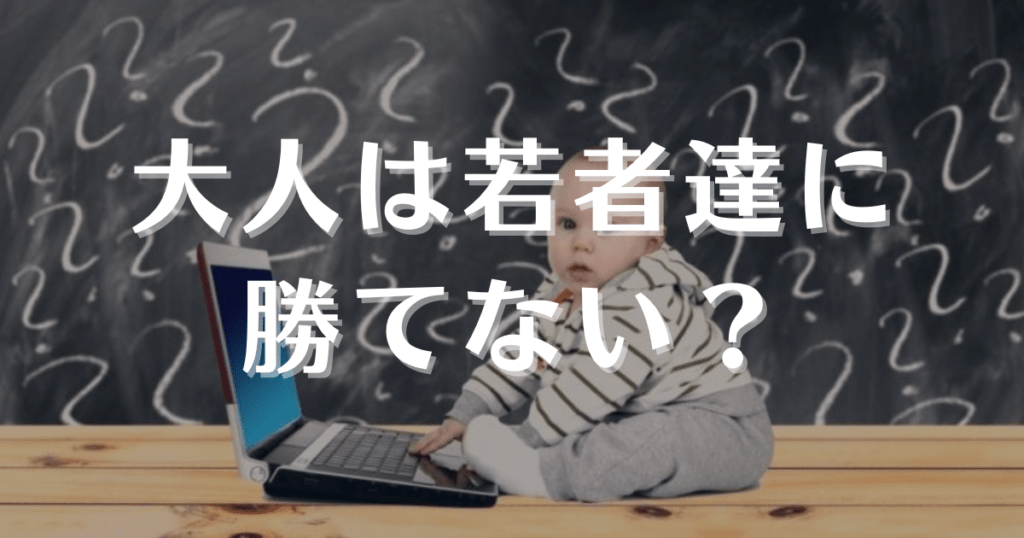
私達は普段、ビジネスにおいてたいてい、同世代かせいぜい±5歳ぐらいの年齢幅を意識すると思います。ところが、実は今、そういうわけにもいかなくなっていて、ことネットビジネスにおいてはもはや中高生以上の人達をライバルとして視野に入れて活動しなければならなくなっています。その理由と、今後どのように対応していけば良いかについて私の考えを解説していきます。
はじめに
私は最近、twitterでたまたまある大学生のアカウントを発見しました。興味を持ったので彼の公式サイト(WordPress)を見てみると、なんと普段私が情報発信のコンサルティングでお伝えしているようなことが高いレベルで実現できており、既に公式サイトのアクセス数も月間16万PVとのこと。
これには驚くと共に、次に思ったのは
ということでした。
その理由について、以下のWikipediaの情報を見て理解することができました。
ーー以下、Wikipediaよりーー
情報社会心理学を専門とする橋元良明氏らによると、日本におけるデジタルネイティブを、
- 1976年前後生まれのIT起業家たちの世代(76世代)
- 1986年前後生まれの世代(86世代)
- 1996年前後生まれの世代(96世代)
に区分し、各世代は大きく異なる特徴を持っていると主張する。
世代別の特徴
1976年前後生まれのIT起業家たちの世代(76世代)
パソコンによるインターネット利用が中心で、携帯電話を補完的に利用している世代であり、インターネット黎明期に積極的に関わった。
1986年前後生まれの世代(86世代)
携帯電話によるインターネット利用が中心の世代である。
1996年前後生まれの世代(96世代)
日本の先進的なモバイルブロードバンド環境を背景に、様々な携帯通信機器を利用して動画コンテンツを視聴するとともに、クラウド環境での集合知(衆合知)を活用する世代であり、「ネオ・デジタルネイティブ」とも呼ばれる。
物心ついた頃から学生時代にかけて携帯電話やホームページ、インターネットによる検索サービスに触れてきた世代を「デジタル・ネイティブ第1世代」、ブログ、SNS、動画共有サイトのようなソーシャル・メディアやクラウドコンピューティングを使いこなし青年期を過ごした世代を「デジタル・ネイティブ第2世代」と分類する意見もある。
ーー以上、Wikipediaよりーー
この後半の記述の部分で、
「動画コンテンツを視聴するとともに、クラウド環境での集合知(衆合知)を活用する世代」
がポイントです。
この96世代の解説を見るとどうしても「新型ターミネーター」と彷彿とさせる内容となっているようで仕方がありません😅
スペックが違いすぎます!
あなたがもし私と同じ1970年代生まれであれば、子供の頃、説明書をあまり見なくても電化製品の操作方法を覚えることができたのではないでしょうか?
あなたがもし1970年以前の世代であれば、説明書が無いと、もしくは使い方をイチから教えてもらわないと、電化製品の操作方法が理解できないのではないでしょうか?
私が今、「ネオ・デジタルネイティブ世代」に驚異と可能性を感じているのは、彼らはSNSの使い方を説明書無しに理解できるだけでなく、「フォロワーの増やし方」「SNSの同士の連携方法」といったことも、素で理解しているのではないか?と思う節がある点なのです。
その疑問は、このWikiPediaの記述を読んで、ようやく納得できたのです。
「動画コンテンツを視聴するとともに、クラウド環境での集合知(衆合知)を活用する世代」
とは、例えば写真や動画でコミュニケーションするSnapChatやTikTokを好んで使っている点、大人から教わらなくても、自分でネット検索したりYouTube動画を見たりして何でも調べて問題解決できる点、といったことを見事に表現しています。
大人たちが講座や塾で寺子屋形式で足並み揃えて学習している間に、彼らは瞬足でネット検索し、友達と情報共有しながら、どんどん課題を解決していっているのです。感覚的には、自分と友達の「脳」がオンラインで繋がっていて、常に会話ができる状態。まずは友達に聞いてみて、友達も知らなければネット検索。
もしくは、その逆パターン。
このようにして、「ネオ・デジタルネイティブ世代」は自分が持っていない情報をフル活用しながら日々の生活を送っているわけです。
彼らの資産はお金よりも友人とのネットワークや自分のSNSのフォロワーやSNSアカウントそのもの。
それらが最終的にお金に変わる、ということを肌で理解しているようです。
そして彼らには無尽蔵に時間があります。
大人達がブログやSNSに1日1記事をやっとアップしている間に、彼らはブログに数記事、YouTubeに動画1件、Twitterでは1日平均20ツィートと、とても太刀打ちできないようなボリューム感でアウトプットしています。
まるでSNSが体の1機能として搭載されているのか、もしくは脳の中にSNSがインストールされているかのような感じ。
つまり、「ネオ・デジタルネイティブ世代」とは、「SNSネイティブ世代」「クラウドネイティブ世代」とも言い換えられると私は考えています。
ネットビジネスでは大人が若者達に勝てない理由
 私が若者達のSNSを見ていてもう1つ気づいたことがあります。
私が若者達のSNSを見ていてもう1つ気づいたことがあります。
ある20歳の現役大学生は、自分が受験勉強をしていた頃、偏差値を40台から70台に上げることができたので、その方法をYouTube動画で語ったところ、なんと60万回以上の再生数を獲得。そしてある20代の青年は、自分の転職経験をシェアし、多くのフォロワーを獲得。
2人に共通している点は、まだ『大成功者』として社会で認知されているわけではないにもかかわらず、沢山のフォロワーを獲得することができている、ということ。
その理由について考察してみたところ、次のような結論に達しました。
その根本的な理由は、「シェアの速さ」にある、ということです。
シェアの速さが全然違う

彼らは、自分の日々の経験から、小さな成功体験、失敗体験を、どんどんSNS上にアップしています。
同世代の層からしてみれば、身近な存在でありながら自分よりも1歩〜3歩ほど先を行く彼らが情報をシェアしてくれることにより、「自分も頑張れば追いつけるかも?」という期待感を持っているはず。
また、今日や昨日起こったばかりの出来事なので、同じことをすれば再現できる可能性が高い、つまり再現性が高い、ということなのです。
一方で、既に世の中で認知されている『大成功者』達は、一昼夜でその領域に達することができたわけではなく、何年も何年も地道な努力を続けた結果、今の成果を得ることができています。
すると、大成功者が今日起きたことをシェアしてくれても、まだゼロイチの段階の人たちからしてみれば、雲の上の話なのでまだピンと来ないし、大成功者がゼロイチの時の話をしても、もう10年、20年も前の出来事なので、同じことをしてもかなり再現性が低い、という問題があるわけです。
つまり、考え方やマインドセットは参考になっても、ノウハウとしては参考にできない、ということです。
例えば、ソフトバンクの孫正義さんが「ビジョンファンドが真っ赤っ赤です。原因は●●でした。」という情報をシェアしてくれても、一般人には「へぇ〜」というだけで自分のビジネスに即反映できるわけではないです。
逆に孫さんは駆け出しの頃、渡米してインベーダーゲーム機の販売を手掛けて一山稼いだという逸話がありますが、この話を聞いて今実行しようとしても全く再現性が無いわけです。
もう1つ、大人達が若者達に勝てない理由があります。
可処分時間の差で圧倒的に不利である

それは、「可処分時間の差」です。
人生の中で、自分が自由に使える時間が最も多くある時期は、プータローを除くと、大学生か老後になります。社会人になると昼間は会社に時間を取られるし、職場ではかなりのプレッシャーがあるので、クタクタになって帰宅した後、副業に割くことができる時間はそうあるものではありません。
資本や規模の大きさが有利となるオフラインのビジネスとは違い、少資本からスタートできるネットビジネスの場合、最も重要な経営資源は、経営者の「時間」です。
特に自分のアイディアを具現化するスタートアップの段階では、いかに経営者が自分の業務に注力できるかにかかっています。
すると、
- 生活費はある程度親が出してくれる
- 大学の講義もそこまで忙しくない(特に文系)
- お金を稼ぐことへの制約も特に無い
という条件が揃っているのが大学生なのです。
60代以降のリタイヤ世代はそもそもデジタルネイティブではないのでITに疎いし、どうしても未来へ向けてのアイディアも乏しくなってしまいます。
つまり、ネットビジネスを行うのに最も有利なのは大学生なのです。
その他の世代も含めて時間の作りやすさをランキングしてみると、
という感じではないかと思います。
という私も、ショッピングカートのレンタルシステムを開発したり@SOHOを開発したりできたのは③の独身時代の時であり、会社に通いながらも土日はフルに自分のために時間を使うことができました。
そして独身サラリーマン時代に土台を作って独立起業した後に結婚したので、うまく軌道に乗せることができたのではないかとも思います。私が結婚したのは29歳の時ですが、もし20代前半で結婚していたら子育てやら何やらで副業なんてできなかったかもしれません。
あるネオ・デジタルネイティブ世代の若者は毎日、
- ブログ記事1本(3,000文字前後)
- YouTube動画1本
- twitter投稿30回
をこなしています。
彼はまだ独身なので24時間を自分のためにフルに使えるからこそこれが実現できるとも言えます。妻子持ちの既婚者であればまず同じような時間の使い方はできないでしょう。
うまく人を使って外注化すれば実現可能かもしれませんが、それができるのは既にある程度資金に余裕がある人だけ。
まだ土台ができておらずこれからという方は、結局のところ副業に時間を割くことすらままならず、永遠にサラリーマン生活から抜け出せない、ということになってしまいがち。
それでは、アラフォー世代以降の人達は、どのようにして戦っていけば良いのでしょうか?
ネオ・デジタルネイティブ世代から学び、共存すること
これはやはり、「ネオ・デジタルネイティブ世代から学び、共存すること」だと思います。
意識して若い世代の動向を把握し、彼らと接点を持ち、彼らの能力を認め、そして交流を図ることです。
私達が唯一勝っているのは、「過去の歴史を肌で体感している」ということ。バブル崩壊、ITバブル崩壊、ライブドアショック、リーマンショックといった経済的な事件の渦中を体験しているので、その経験をもとに意思決定できるという優位性を持っています。
例えば検索エンジンの歴史を辿ってみても、ネオ・デジタルネイティブ世代が物心ついた時には既にGoogleが検索エンジン業界でNo.1の地位を確立していたので、ヤフーとの小競り合いも含めた検索エンジンの発展の歴史を語ることはできません。
但し、ITのオペレーション能力と環境への適応能力は圧倒的に彼らのほうが上なので、そこは彼らから徹底的に学ぶことです。そしてSNSの使い方も若い世代から学ぶことです。
そしてそれを吸収することができれば、アラフォー以上の世代にも明るい未来が待ち受けています。
英語にしてもゲームにしても大人よりも子供のほうが吸収が早いので、それと同じような感覚で捉えれば良いのです。
そう考えてみると、ワクワクしてこないでしょうか?
関連記事

 このサイトのコンテンツは現在進行系でアップデートしています。
このサイトのコンテンツは現在進行系でアップデートしています。
②中高生
③社会人(独身)
④社会人(既婚子供なし)
⑤社会人(既婚子供あり)